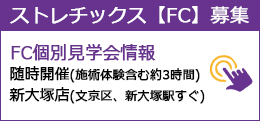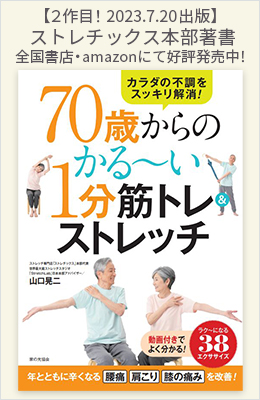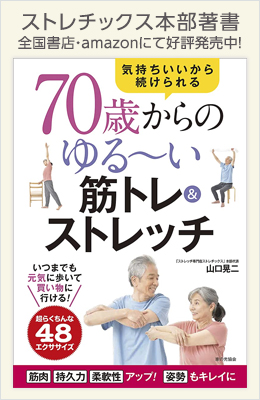はじめてセルフストレッチを本格的に行いたい方に向けて、ストレッチ専門店ストレチックスでお客様にご提案している「シンスプリント・すね痛の緩和」に役立つストレッチのひとつをご紹介します。
重点部位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん)
●すねの筋肉、前脛骨筋の機能
私たちの脚は膝下の下腿(かたい)、膝上の太ももの側を大腿(だいたい)という呼び名に分けられています。
すねである前脛骨筋はその下腿の、前側の部分にある筋肉です。
すねといってもぶつけて痛い思いをした時にくらいしか意識をしないことか多いでしょうか?
ご自身のすねやふくらはぎをさわってみて骨が2本あることは確認できると思います。
中央にある太さを感じる骨を脛骨(けいこつ)、外側にある骨を腓骨(ひこつ)といいます。
名前で想像がしやすいですが、脛骨についている筋肉が前脛骨筋です。以前紹介したコラムにある、ふくらはぎの筋肉などと連携して足首の動きをコントロールしています。
すねとふくらはぎは表と裏の関係です。どちらかが硬くなりすぎていればその対称なる側が余分に活動をしなければならなくなります。
前脛骨筋の動きをよくすることでふくらはぎの筋肉やその他の下腿の筋肉の頑張りすぎを抑えられ、足の疲労軽減や傷害の予防にもつながります。
前脛骨筋は脛骨と腓骨のあいだに縦長についている筋肉です。
膝の下あたりから下側に向かって走行していて足首を通り越し、足の甲の内側を通って土踏まずの内側部分までついています。
前脛骨筋
起始:脛骨外側面・下腿骨間膜
停止:内側楔状骨・第1中足骨
機能:足関節の背屈・内反

この筋肉の大きな役割は足首を上に向けることです。
この動きを足関節の背屈といいます。
内反(ないはん)という動作は足首を内側に捻る動きです。
前脛骨筋を使って自分の首を動かしてみましょう。
椅子、もしくは床に座った状態で足を前に伸ばしてつま先を反らせるように上に向けるとすねの上で縦長の筋肉が盛り上がると思います。
あまり機会がないかもしれませんが、すねをもみほぐすと痛いと感じる方と、気持ちよいと感じる方に分かれる傾向にあります。
同じ下腿の部分でも、ふくらはぎに比べると硬いことがわかります。
「すね肉の煮込み料理」があるように人間でもじっくり緩めないとならない部分ではないかと思います。
前脛骨筋は肩コリのように疲労度が現れにくいため、気が付かない場合が多いようです。
指で押してみると押し込むことができないくらい固まっていることがあります。
ふくらはぎはストレッチやマッサージをすることが多いと思いますが、表側を緩めるという意識は持ちにくいかもしれません。
脛骨と腓骨のあいだの見てわかる部分なので、手指でほぐしていく、ゴルフボールなどを当ててほぐしていくなどで硬さを緩めていくことが適していると思います。
●前脛骨筋の日常での使われ方
前脛骨筋の役割はつま先を持ち上げることなので、人間が二足歩行であるくことに関連しています。
歩くときに足首を動かすことはもちろんですが、床から立つ、椅子から立ち上がるときにはすねが足の甲に向かって重心を足に乗せることができます。
坂道、スキーやスケート、登山などで山道を移動するときには足首が前傾して深く曲がることもあり、下りでは後ろに倒れないようにブレーキを掛けるように働きます。
そのような使い方をした後に筋肉痛になった経験のある方もいるのではないでしょうか。
また、足底のアーチの一つである内側縦アーチ(土踏まずの内側のライン)の維持に働いているので、歩く、走る際に衝撃を吸収しています。
前脛骨筋が疲労して機能が弱くなるとアーチが下がってしまうことや、すねに痛みが出たりする場合もあります。
●前脛骨筋の機能低下を防ぎましょう
つま先が上がらない不具合で思い当たることが多いのが「つまずく」です。
段差を越えるとき、段差がなくてもつま先が引っかかり転びそうになってヒヤッとしたということがご自身、また周りの方にはいないでしょうか。
つま先が持ち上がらなければ足をズルズルと引きずるようになってしまいます。
前脛骨筋の機能を上げて転倒予防をしていきましょう。
前脛骨筋の筋力トレーニング
・トゥレイズ
座位、または椅子に座ります。
足の甲を膝に近づけるように上に持ち上げます。
つま先が上に反ってこないようにして行いましょう。

●前脛骨筋のストレッチ
前脛骨筋が硬くなっているかは足首の動きでチェックすることが出来ます。
つま先を持ち上げる筋肉なので下向きにしてみましょう。
このとき、足が真っすぐに下に向かずに内側に向かって捻ってく動作になっていると前脛骨筋が硬くなっている傾向があります。
膝下が外側方向に偏りますので小指側に体重が乗りやすくなります。

足首の硬い方はあまりストレッチ感がでにくいかもしれません。
ほぐしと合わせて行えるとよいと思います。
・椅子に座ってできる前脛骨筋のストレッチ
椅子などに座って片足のつま先をもちます。
つま先を下に向かって引き下げます。
足首の前側からつま先までを離すようにして伸ばします。

・床に座ってできる前脛骨筋のストレッチ
床に正座で座ります。
伸ばす側の膝を上に持ち上げ床から浮かせます。
つま先から膝を遠ざけるようにして伸ばします。

・立位でできる前脛骨筋のストレッチ
片足のつま先と足の甲を床につけます。
すねを前に押し出すようにして伸ばします。

●足首全体でも動きを見ていくことも必要
すねの疲労を常々感じているという方はこの前脛骨筋のみではなく足首の動き全体で考えることも必要です。
足首の負担を減らす一つは皆さんが履く靴があげられます。
なかなか難しいことですがまずは足の形に適したものを選ぶことが大切です。
そして紐靴を使用している方はできる限り毎回、靴紐を締めなおして履くことが理想です。
自身の足と靴が一体になるようにしておけば足に余計な重さをかけずに足首を動かすことができるので前脛骨筋への負荷も軽減されます。
手間のかかることですが余裕がある際はやってみましょう。
また、靴の底(ソール)が大きく削れている場合は早めに新調するか補強しましょう。
もともとの足の形、重心により削れてくる部分は異なります。
すねの部分にかかる負担を考えると外側が削れている場合がその負担が多いと思います。
自然に立っているとき、片足になるタイミングの時、足の土踏まずとかかとが内側に向かって落ちない、倒れないように支えている役割をしています。
かかとの位置の傾きが大きくでることで、そのバランスをとるために負荷がかかることがあります。
靴の問題か、足の問題かはどちらが先かといいにくいですが、体重を支える部分なので少し気にかけてみるのはいかがでしょうか。
すねの負担を軽減する2つ目のポイントは当たり前のことかもしれませんが、足首の関節が正しく動くかです。
部分的な硬さや骨格の位置により気が付かないうちに関節が動きやすい方向に優先に動いてしまう点があげられます。
足首に距骨(きょこつ)という骨があり、これは滑車のように動いています。
先ほど出てきた脛骨と腓骨が上にありますが、この骨の間にはまり込むように距骨が動くことでスムーズに足首が上に向かって持ち上がるようにできています。
足首を自然に上に向かって持ち上げてみてください。
このとき真っすぐに持ち上がっているでしょうか。足先が斜め方向に向かっていたり、反りかえったりしてはいないでしょうか。
また、つま先、指先が大きく上に持ち上がっていないでしょうか。
このような場合は滑車となる部分が適切に動かずに、逃げ道をつくって動いていることが予想されます。

★足の内部には細かい骨が存在します
個人差が大きい部分なのでどの部分をどのようにしたらよくなるまでは解説がしにくいですが、共通していることは、つま先が反りかえらずに、真っすぐに向かって上げる動きを覚えることです。
そのためには練習です。
自分の足首が真っすぐ上がっていくように一つの運動として行うことです。
ただ、やはり足首が詰まる感じがある、前脛骨筋に極端に力が入ってしまうことがあると思います。
それぞれ差がでることですが、すねを少し内側に向かって捻るようにして、足の甲がスムーズに上に持ち上がるようであればその形で動かす、アキレス腱、くるぶしの周り、足首と足の甲の境目あたりをマッサージしていくなどで、動きやすくなることがあります。
●前脛骨筋の関連する傷害
すねの周囲に痛みが出る症状に、シンスプリントというものがあります。
これは脛骨過労性骨膜炎といった症状で、すねの前側に痛みが出るタイプと後ろ側に痛みを生じるタイプがあります。
前側に痛みがあるタイプが前脛骨筋の関連が考えられています。
シンスプリントの主な原因はオーバーユース、過剰に使い過ぎてしまうことがあげられます。
とくランニングの頻度が多い方やバスケットボールなどジャンプや細かいステップが多い競技に起こりやすいといわれます。
また中高生など部活での運動量が増えたという影響で起こることもあり年齢を問わず生じることがあるものです。
予防としては紹介した前脛骨筋のストレッチや筋肉を緩めるようにして疲労の蓄積をさせないようにすることです。
スポーツであれば休養日を設けて負担をかける割合を減らすようにしてオーバーユースにならないようにしましょう。
また、使用しているシューズが足をしっかりと固定されないようなものであったり、クッション性が落ちてきたものであったりすれば適したものに履き替えることも必要です。
痛みが出ていれば安静に、アイシングをして炎症を収めるようにすること処置の一つだと思います。
前脛骨筋の負担を軽減するためにはこの筋肉だけでなくその周囲の筋肉のケアも必要です。
対になる機能をもつ筋肉であるふくらはぎの腓腹筋、ヒラメ筋、足底のアーチを守る足底筋のストレッチやトレーニングなども行えるとよいと思います。
・タオルギャザー
フェイスタオル程度のものを床に置き、足の裏で手繰り寄せます。
指先から土踏まずを使って握り込むようしましょう。
足底の筋群のトレーニングです。

今回紹介したこと以外にも、足の形、膝の向きなどからも影響を受けます。
肩こりや腰痛に比べると少し足を捻っただけのように、あまり注目されない部分かもしれません。
足元は体を支える土台になる部分です。
立つ、歩くという私たちが移動するために必ず使う部分です。
ストレッチや足首周囲のマッサージも取り入れて大切に使っていくことが必要な部分だと思います。
▼ 東京都文京区・豊島区・北区・中央区、札幌市、埼玉上尾市、滋賀県草津市、近江八幡市、山口県、高知市、長崎県にお住まいの方へ。
整体、フィットネス以上に”癒し感””運動効果”が持続!
疲れ・コリ・姿勢改善・ダイエット・スポーツ前後におススメ。
新大塚駅、千石駅、白山駅、茗荷谷駅、春日駅、東十条駅、東日本橋駅、埼玉上尾駅、札幌駅、滋賀草津駅、近江八幡駅、山口駅、高知駅、長崎西諌早駅からすぐのストレッチ専門店ストレチックス


 ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介
ストレッチ専門店ストレチックスのご紹介











 ストレッチ専門店
ストレッチ専門店